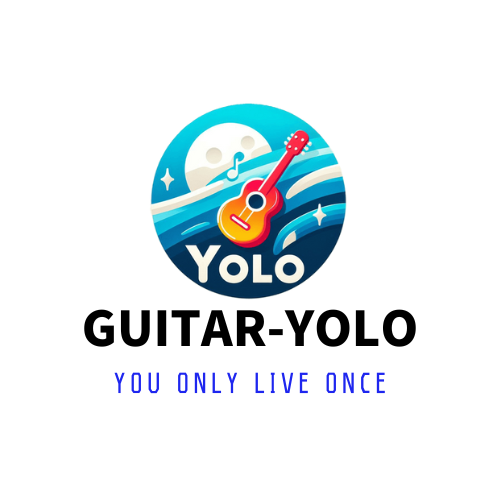セーハで挫折しそうになったこと、ありませんか?
「自分だけできない」「どうしても音が出ない」そんな経験は、実は多くの人が通ってきた道です。
この記事では、筆者自身が悩んだ末にたどり着いた「セーハができるようになる7つの秘訣」を紹介します。
少しでも前に進みたいあなたのギターライフの手助けになればうれしいです。
そもそもセーハとは?


ギターを始めて最初に多くの人がつまずくのが、「Fコード」や「Bコード」に代表される“セーハ”です。
これは人差し指1本で複数の弦を同時に押さえる奏法で、ギター初心者にとって最初の大きな壁とも言えるでしょう。正式には「バレーコード(Barre chord)」と呼ばれています。
一見すると簡単そうに見えるこのフォームですが、実際にやってみると「音がまったく鳴らない…」「指がつりそうになる」「握力が足りない気がする」といった悩みにぶつかる人が続出します。
ですが、安心してください。こうした悩みはギター初心者なら誰もが一度は経験するものです。
むしろこの壁を越えることで、コードの幅が広がり、演奏の自由度も一気に増します。
これは多くの初心者が経験していることですが、「毎日地道に続けていたら、ある日急に音が鳴るようになった」という瞬間が訪れます。
最初はうまくいかなくても、無意識のうちに指や手首の動きが洗練されていき、気がついたら自然と押さえられるようになるのです。
焦らず、今日も少しだけセーハに触れる。それが上達への近道です。
セーハがうまくいかない原因


「指の力が足りないから」と思われがちですが、実はフォームや力の入れ方、ギターとの相性も大きく関係しています。
- 指の関節が曲がっていることで、押さえる力がうまく伝わらず、音がビビったり鳴らなかったりする。
- 親指の位置が悪く、力のバランスが崩れてしまう。
- ネックの太さや弦の高さが合っておらず、余計な力を使ってしまっている。
また、これらの要素は単独で問題になるだけでなく、複数が重なることでさらに難易度が上がります。
たとえば、親指の位置が不安定な状態で指の関節が曲がっていれば、音が鳴るはずもありません。
つまり、「指の力」だけに注目してしまうと、本質的な原因を見逃してしまうことがあるのです。こういった小さな要素が積み重なって「セーハができない」を引き起こしていることを理解することが、上達への第一歩です。
セーハを成功させる7つのコツ


1. 指をまっすぐにせず、少し斜めにする
指を真っすぐ置こうとすると関節が浮いてしまい、音が出ません。斜めに寝かせて置くイメージで、関節の硬いところで押さえると、力を無駄なく伝えることができます。また、指の腹全体ではなく、骨の出っ張っている部分を使って押さえる意識を持つことで、より安定して音を鳴らすことができます。
2. 指の関節は柔らかく使う
関節をカチカチに固めてしまうと、無意識のうちに指が反ってしまい、特に1・2弦がビビってしまう原因になります。「力を入れすぎない」ことが意外と大事で、適度に力を抜いて、必要な場所にだけ力を入れる“コントロール”が重要です。
3. ギターのボディを体に引き寄せる
セーハを押さえようとするほど、力が入ってギター本体が前に動いてしまうことがあります。体にギターを密着させるように構えることで、腕の力が分散されずにしっかりと指板に届くようになります。ストラップを使って位置を固定するのもおすすめです。
4. 親指の位置はネックの裏の真ん中
ついついネックを握りこんでしまう人も多いですが、親指はネックの真後ろあたりで軽く支える程度が理想です。親指を立てる角度や位置を少し変えるだけで、セーハの安定感がグッと増すこともあります。
親指に力が入りすぎている方は親指を離して鳴らす練習もしてみてください。
ギターのボディがしっかり押さえられていれば親指は本当に添えるくらいで十分なことに気付けます。
5. 弦高が低いギターを使う
初心者用ギターの中には、弦が高すぎて押さえにくいものもあります。初心者で弦高が高いのは致命的です。
弦高が高いと、セーハに限らず全てのコードで力が必要になり、指が疲れてしまいます。楽器店で調整してもらうことで、押さえやすくなる場合もあります。
6. いきなり1フレットじゃなく、3フレット付近から
ネックの下の方(1フレット)は押さえるのに力が必要です。まずは3フレット付近で練習して、感覚を掴みましょう。フレットが狭すぎない位置で練習することで、フォームの確認や修正がしやすくなります。
7. Fコード以外のセーハコードから挑戦する
Fコードは押さえる弦が多く、初心者には難しいコードの代表格です。まずは「Bm」や「Am7(セーハ型)」などの簡単なセーハから始めることで、少ない弦から感覚を掴み、徐々にステップアップしていくのが効果的です。
セーハができるようになる練習法


セーハの練習では、まず音がきちんと出ているかどうかを丁寧に確認することが大切です。
全弦一気に鳴らそうとするのではなく、6弦から1弦まで1本ずつ確かめながら「ちゃんと鳴っているか」「ビビっていないか」を耳で確かめましょう。
特に初心者の場合、1弦や2弦の音が出にくいことが多いため、弱点を見つけて集中して修正する意識を持つと上達が早まります。
この確認作業をすることで、自分のどの指がうまく押さえられていないのか、またフォームが崩れていないかを視覚的・聴覚的にチェックできます。
毎回の練習前に数分だけ取り入れるだけでも、効果は抜群です。
大切なのは“毎日触れる”こと。長時間でなくても良いので、毎日少しずつ練習することで脳と指の動きが連動し、無理なく弾ける状態に近づいていきます。
焦らず、今日も少しだけセーハに触れる。それが遠回りに見えて、最も確実な近道です。
セーハがうまくいかないギター側の問題とは?


セーハがうまく押さえられないとき、実は「ギター自体」に問題があるケースもあります。
弦高が高すぎるギターを使っていないか?
初心者向けの安価なギターには、弦と指板の間隔(=弦高)が高いものもあります。弦高が高いと、それだけ指に負担がかかり、音が出にくくなってしまいます。
初心者には絶望的な状況になってしまうので、練習しても綺麗に音が鳴る気がしない場合はチェックしてみてください。
1つの目安として、12フレットの隙間が2.5mm~3mmであれば大丈夫です。
ネックが太すぎる・反っている
手が小さい人にとってネックが太いギターはセーハが難しく感じやすいです。また、ネックが反っていると、特定の弦だけ音が出にくくなることも。
フレットが削れている・メンテナンス不足
長く使っているギターや中古ギターでは、フレットが摩耗していたり、ナットやサドルの調整が不十分なケースも。音のビビりや押さえにくさの原因になります。
もし「練習しても全然改善しない」と感じたら、一度楽器店などでギターの状態をチェックしてもらうのもおすすめです。
調整した後のギターは本当に別物です!
あなたのギターのコンディションは大丈夫ですか?
セーハができないときの対処法


コードを簡略化して楽しむ
どうしても弾けないときは、「Fmaj7」や「Fadd9」などの簡易コードを使って、まずは“楽しむこと”を優先しましょう。
こうしたコードは押さえる指の本数が少なく、力をそれほど必要としないため、音がきちんと出やすいというメリットがあります。
また、簡易コードを使うことで演奏の楽しさを感じながら、自信をつけていくことができます。
「音が鳴る」という成功体験は、練習を継続するうえで大きなモチベーションになります。
一時的な対処法ではありますが、セーハ習得へのステップとしては非常に有効です。
ギター教室という選択肢
1人で限界を感じたら、やっぱりプロに見てもらうのが最短ルートです。
当然ながら数々の初心者を見ているので、具体的な改善案を出してもらえます。
単発から受けられるオンラインギター教室もありますので行き詰った際には是非活用してみてください。
関連記事:オンラインギター教室おすすめ5選
まとめ
セーハはギター初心者の最大の難関かもしれません。 でも、正しいやり方を知って、少しずつ練習すれば必ず乗り越えられます。
セーハに関しては練習していたらいつの間にか弾けるようになっていたという声が多いので、是非明日を楽しみに今日も練習してもらえればと思います!
毎日少しずつ、焦らず、楽しみながら弾いていきましょう!