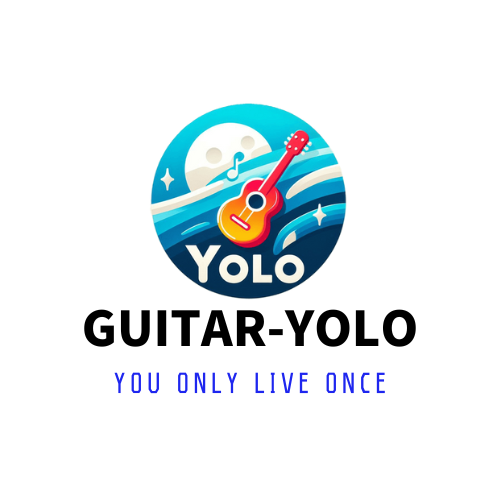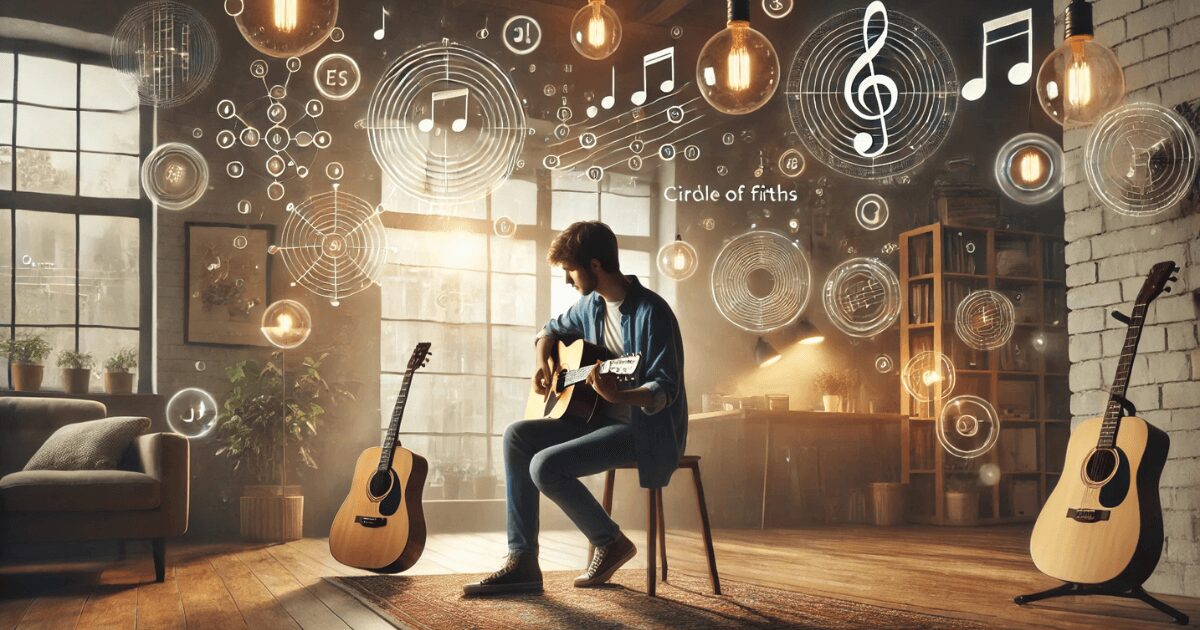ギターでコードとメロディを同時に弾くうえで大事なのはメロディ音をコードの一番高い音にするということです。
「ギターでコードとメロディを同時に弾けたら楽しそう!」
ギターでコードとメロディを同時に弾くうえで必要な音楽理論

まずギターでコードとメロディがを同時に弾くうえで以下の3つの知識を知っておく必要があります。
コードの構成音を理解しよう
- コードは3つ以上の音を同時に鳴らす和音
- 例:Cメジャーコード → C(ド)、E(ミ)、G(ソ)の3音
- ルート(根音)、3度、5度の音で作られる
- コード名から「どの音が含まれているか」を知るクセをつけよう
キーとスケールの基本
- スケール=音階、その曲でよく使う音の並び
- 例:Cメジャースケール → C D E F G A B
- キーCの曲なら、基本的にこの7音でメロディとコードが構成される
- ダイアトニックコード:スケール内の音だけで作られたコード群
- Cメジャーキーなら → C, Dm, Em, F, G, Am, Bdim
ハーモニーとコード進行の基本
- コード進行=コードの並び方
- よく使われる進行 → I-IV-V進行(例:C-F-G)、I-V-vi-IV進行 など
- 特に**I, IV, V(トニック・サブドミナント・ドミナント)**の役割を理解
- メロディとコードを合わせるときは、進行の流れを意識しよう
ストロークでメロディが聴こえてくる弾き方

メロディ音をコードのトップノートに置く
- ストローク時でも、意識的に1弦や2弦にメロディ音を配置する
- 高音弦を強めに弾くことで、メロディラインを際立たせる
コードトーンを優先してアレンジ
- メロディの音がコード構成音(コードトーン)なら不協和が少ない
- コードフォームを工夫して、メロディ音を含めた形に変えてもOK
メロディに沿ったリズムで弾く
- メロディの音数によってリズムを変化させる
- リズムを細かくし、メロディの部分だけ高音弦を狙うことでより浮き立たせる
曲のキー、各コードに対する高音弦のドレミファソラシがどこにあるかを覚えると効率よく練習できます。
フィンガースタイルでメロディを際立たせる方法

フィンガースタイルは、親指でベース音を担当し、他の指でコードやメロディを同時に弾くのが特徴です。
- 親指=ベース音(6弦~4弦)、人差し指~小指=メロディ&コード(3弦~1弦)
- 重要なのは、メロディ音が目立つように高音弦をしっかり弾くこと
フィンガースタイルのメリットは、メロディとベース音を独立して動かせるため、初心者でも音を整理しながら練習できます。
初心者が陥りやすいポイントと注意点

コードフォームに縛られすぎない
ギター初心者は、覚えたコードフォームをそのまま使おうとしがちですが、メロディを際立たせるためにはコードフォームを崩していく必要があります
たとえばCコードのフォームでも、5弦と4弦だけを押さえて1~3弦をメロディ用に開放するなど、必要な音だけ抜き出したコードフォームで弾くのが基本となります。
一つのコードをフォームで覚えるのではなく音で覚えるを意識してください。
そのためには指板の理解が重要で指板の音を覚えるのが一番の近道になります。
複雑なTAB譜に惑わされない
プロのソロギター譜やアレンジ譜は、非常に音数が多く難しそうに見えることがあります。
初心者は無理にすべて再現しようとせず、メロディと最低限のコードトーンに絞ってシンプルに練習することが大切です。
タブ譜を使うときに気をつけたいのが、形だけで覚えてしまうことです。
指の動きばっかり覚えて、音の流れを意識しないままだと、曲が変わるたびにまた一から覚え直す…ってことになりがちです。
ですがちょっと理論をかじりつつ、音のつながりを意識して体で覚えていくと、いろんな曲にも応用がきくので、自由に弾ける幅がぐっと広がりますよ。
「理論は理解できたけど、実際に演奏となるとどうしてもうまくいかない…」
「動画だけでは限界を感じている」
そんな方には、ギター教室で直接アドバイスを受けるという選択もおすすめです。
単発レッスンを採用している教室もあるので是非参考にしてください。
関連記事:2025年版オンラインギター教室おすすめ人気教室5選
まとめ
メロディ音をコードの中で一番高い音(トップノート)にする
ギターでコードとメロディを同時に弾く際にもっとも大切なのは、メロディ音をコードの中で一番高い音(トップノート)として配置することです。こうすることで、コードの響きを保ちながら、メロディが自然に耳に届きやすくなります。特に高音弦(1弦や2弦)にメロディ音を持ってくるよう意識すると、ストロークでもフィンガースタイルでもメロディが埋もれず、しっかりと浮き立ちます。
コードの構成音を理解し、指板で見えるようにする
コードをただ形で覚えるのではなく、どの音がコードを構成しているか(ルート・3度・5度など)を理解することが大切です。その上で、それぞれの音が指板上のどこにあるのかを把握しておくと、メロディとの組み合わせやアレンジの幅が一気に広がります。指板を「暗記」するというよりは、見える・探せるようになることを目指しましょう。音と場所が結びつくと、演奏もスムーズになります。
弾きたい曲を研究し分解して練習する
「この曲を弾けるようになりたい!」と思ったら、まずは曲をよく聴いて、構成やメロディ、コード進行を分解してみましょう。いきなりフルアレンジで弾くのは難しく感じるかもしれませんが、メロディだけ、ベースラインだけ、コードだけ…とパーツごとに分けて練習することで、全体像が見えてきます。少しずつ組み合わせながら、最終的に1本のギターで完成された演奏ができるようにしていきましょう。
ぜひ理論を活かして、ギター1本で曲を奏でる楽しさを体感してください!