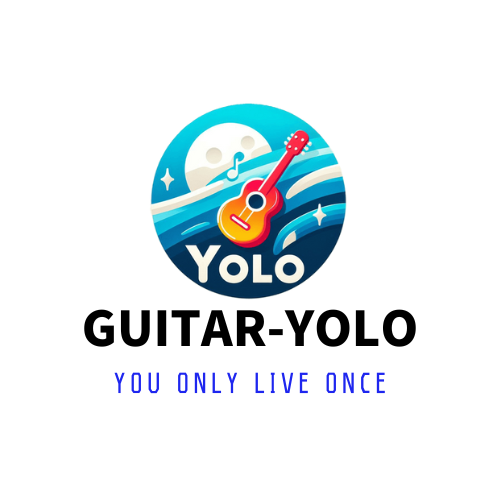ギターをもっと自由に弾きたい!
コードやスケールをもっと深く理解したい!
そんな悩みを解決するのが「度数」の知識です。
度数を理解すれば、コードの成り立ちやスケールの構造が見えてきて、ギターの演奏がより楽しくなります。
ギターをもっと好きになってもらうため、度数を覚える方法をまとめたので是非参考にしてください。
度数とは?まずは基礎を理解しよう!

度数とは音と音の距離
ギターの「度数」とは、ある音(基準となる音)から見た 相対的な位置関係 を表すものです。
例えば、Cメジャースケール(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ)の場合、次のように度数が割り当てられます。
| 音名 | 度数 |
|---|---|
| C(ド) | 1度 (Root) |
| D(レ) | 2度 (9th) |
| E(ミ) | 3度 (3rd) |
| F(ファ) | 4度 (11th) |
| G(ソ) | 5度 (5th) |
| A(ラ) | 6度 (13th) |
| B(シ) | 7度 (7th) |
この度数を理解すると、コードの構成やスケールの仕組みが 視覚的、感覚的に 把握しやすくなります。
ギターで度数を覚えるための3つのコツ
ギターの指板上で度数を覚えるのに役立つ 3つの方法 を紹介します。
5弦・6弦のルートを基準に考える

度数を覚える時、 5弦・6弦のルート音 を基準にすると度数の位置関係が分かりやすくなります。
まずは6弦ルートからみた度数の位置関係を覚え、次に5弦ルート、4弦と順番に覚えていくと覚えやすくなります。
度数の位置関係のPDFを載せておきますので、欲しい方はご活用ください。
この度数の位置関係を一度覚えてしまえばギターの特性上、どんなキーでも同じ形で考えられるようになります。
メジャースケールの形で覚える
メジャースケールの形を 度数で意識する と、より実践的に使えるようになります。
なぜなら各フレットの音を 「1度・2度・3度…」と度数で考える 習慣をつけると、他のスケールやキーへの応用が簡単になるからです。
例えばメジャーペンタトニックスケールだと、4度と7度を抜くとメジャーペンタとなり、2度と6度を抜くとマイナーペンタとなるのでスケールの習得も簡単になります。
メジャースケールの形で度数の位置関係を覚えることで、各スケールも効率よく覚えることができます。
コードの構成音を度数で覚える
コードの構成音も、度数で理解すると応用が効きます。
例えば、Cメジャーコード(C・E・G)は 1度・3度・5度 の組み合わせ。
主要コードの度数構成
- メジャーコード(C) → 1度・3度・5度(C・E・G)
- マイナーコード(Cm) → 1度・♭3度・5度(C・E♭・G)
- セブンスコード(C7) → 1度・3度・5度・♭7度(C・E・G・B♭)
コードの成り立ちを 度数で考える習慣 をつけると、指板上の音の配置がすぐに理解できるようになります。
覚えた度数を実際に使ってみよう!

覚えた度数を使って 実践的なトレーニング をしてみましょう。
① 簡単なフレーズを度数で考える
例えば、TAB譜でもなんでもいいので歌メロを弾いてみたとします。
このとき「この音は何度の音か?」を意識しながら弾くと、度数が自然に身についていきます。
② コード進行を度数で分析する
「C→G→Am→F」というコード進行を例にすると…
- C(1度)
- G(5度)
- Am(6度)
- F(4度)
このように、コード進行を度数で捉えると「キーが変わっても同じ流れで理解できる」ようになります!
例えば有名な曲で紹介すると以下になります。
- 王道進行(4-5-3-6)が含まれている曲
- subtitle/Official髭男dism
- 勇者/YOASOBI
- 君はロックを聴かない/あいみょん
- ポップパンク進行(6-4-1-5)が含まれている曲
- 前前前世/RADWIMPS
- ワタリドリ/Alexandros
- ZERO/B,z
色んなパターンを覚えておくことで演奏の自由度を上げたり、作曲に役に立つので是非分析してみてください。
度数の覚え方まとめ

- 6弦・5弦のルートを基準に度数を把握する
- メジャースケールの形で度数を意識する
- コードの構成音を度数で覚える
これらの方法を実践すると、指板上の音の関係性が パターン化 され、 アドリブや作曲 にも応用しやすくなります。
地味な練習ですが、もっと自由にギターを弾けるようになるために頑張りましょう!
もっと具体的な練習メニューを組んでもらいたい方は単発からでも利用できるギター教室オルコネがおすすめなので是非チェックしてみてください。